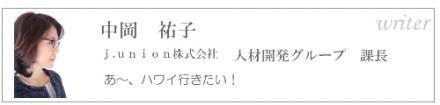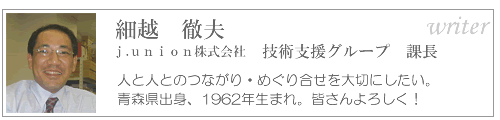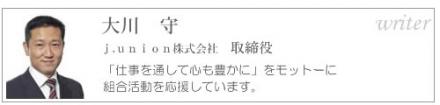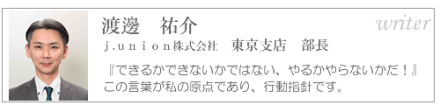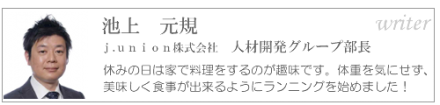よいのかというニーズがあるようです。ダイバーシティは経営戦略であり、働き方改革を実現するための重要な戦術でもある
ため、押さえておきたいキーワードです。にもかかわらず、真の意味でダイバーシティが理解されないまま漠然と取り組んで
いる印象があります。今回、ジャーナルを執筆するにあたり、私なりに整理してみましたので、ぜひ以下の視点でチェックし
てください。逆にいうと、この視点が押さえられていなければ、ダイバーシティを進めようとしても、進んでいるのか進んで
いないのか、どこに向かっているのかもわからず、混乱するはずです。
◆◆ダイバーシティ経営を進めるに
あたってチェックしてほしい視点◆◆
※ダイバーシティのテーマにもいろいろありますが、今回は多くの企業の課題であるジェンダーの観点で語ります。
【スタート】
トップの強いコミットメントがあるか
【ゴール】
目標が明確で、それが組織に共有されているか
【プロセス】
ヘルシーコンフリクトを歓迎する風土があり、それに対応するマネジメント力やコミュニケーション力があるか
【スタート】まず、トップの強いコミットメントがないとダイバーシティは進みませんので、必須条件です。さらには、それ
に継続性があるか、何か具体的なアクションにつながっているかまで含めてチェックしてください。具体的なアクションがな
いと管理職が動かないので、現場は変わりません。トップのコミットメント力が弱い場合は、ダイバーシティの理解を促す必
要があります。ダイバーシティを進めるか否かという議論になった場合は、すでに組織は多様性にあふれており、放置するこ
とは企業の競争優位性を失う可能性が高いことを説明してください。様々な違い(=強み)が埋もれると、イノベーションが
起こりにくくなります。
【ゴール】例えば、ジェンダーがテーマの場合、ゴールは「女性の活躍」です。企業経営としてどこをゴールとするか具体的
に決めてください。活躍の定義は、キャリア(人)の視点からみたら様々ですが、ダイバーシティ経営の視点からみると「指
導的地位に立つ人の割合を増やす」、つまり管理職の増加と捉えて差し支えないと思います。
女性活躍推進法に則って行動計画目標を掲げている組織は、その妥当性、進捗具合のチェックも必要です。セミナーに行くと、
誰も行動計画の目標を知らないといったこともあります。計画期間を過ぎて、古い目標のままネットなどで検索できる状態に
なっていることも避けたいものです。また、従業員の男女比が9:1であるのに、「3年後に管理職の男女比を7:3」にするといっ
た目標も妥当性に欠けると言えるでしょうし、「女性社員が全員研修を受ける」といった目標も、課題を前向きに捉えていな
いと思われても仕方がないでしょう。
【プロセス】研修会場であったある課長の話です。彼は異動で女性の部下が増えました。メンバーには、育児休暇から復帰し
たばかりで仕事に集中できない方がいて、彼女に対して攻撃的な人、そのような問題にしらけている人、そしてそれをおっか
なびっくり眺めている男性メンバーといったふうで、部の雰囲気はとても悪かったようです。前任のマネージャーはとても優
秀でしたが、ついぞその部署をまとめることができず、マネージャー交代になったそうです。就任時の彼の本音は「人のこと
をとやかく言う前に目の前の仕事をしてほしい」でしたが、傾聴ができたので、自分の気持ちは脇に置いてメンバーの気持ち
に寄り添うことにしたそうです。そのため面談が増え本来業務が遅れましたが、結果的に部署に笑顔が戻り、メンバーのモチ
ベーションが高まったそうです。
このように、同じ女性でも価値観は違いますし、違いが多いほど対立が起きます。イノベーションには、健全な対立が欠かせ
ません。しかし、日本の組織や日本人には対立を避ける傾向があります。これではイノベーションは起こりようがありません。
違いをアピールするアサーション力、違いを受け止める共感力、コンフリクトをマネジメントする力。ダイバーシティの仕組
みづくりやアンコンシャス・バイアス・トレーニング以外にも、そのようなコミュニケーション力やマネジメント力を同時に
鍛えていかないと、違いがもろ刃の剣となって組織は混乱するでしょう。
ダイバーシティを進めると、制度や仕組みは複雑化し、組織はまとまりや一体感に欠け、現場の管理者の負担が増えます。単
に違いを増やして、あとは現場にお任せでは、組織はストレスをためます。ダイバーシティは終わりなき旅といわれています。
旅にハプニングはつきものですが、ハプニングの連続も困りものです。しっかり準備して出発しましょう。