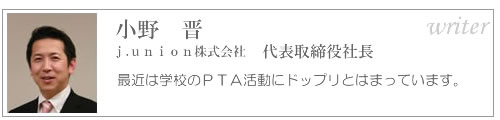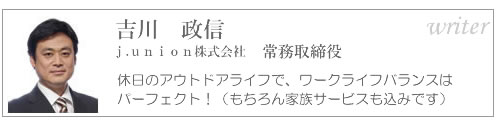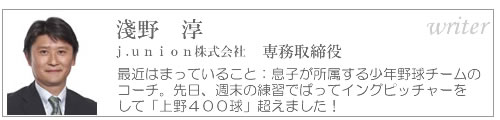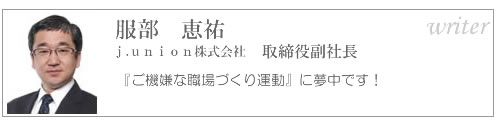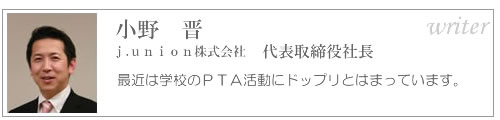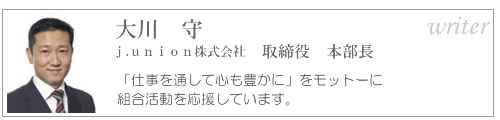■ 四、 われわれの成果は何か?(前回の続き・・・)
~成果は常に自分たちの外にある~ (ドラッカー 生涯問い続ける5つの問い)
----------------------------------------
前回の概要
○ 労働組合などの非営利組織の成果は、つねに自分たちの外にある。
【人々の行動、境遇、健康、希望、そして彼らの適性と能力】の向上などを成果と定義する。
○ そのために
1)外側(相手・顧客)を定義する。
2)外側(相手・顧客)が何を価値と考えるかを調査する。
3)価値を満たす手段・方法を考えて実行する。
4)効果検証。外側の【行動、境遇、健康、希望、適性、能力etc】の向上を調査する。
○ 組織の使命に基づき、成果をより具体的に定義する。
----------------------------------------
●効果検証
組合員の【行動、境遇、健康、希望、適性、能力】が向上しているかを定量的・定性的に
調査し、向上・改善したか(成果をあげたか)どうかを確認しなければなりません。
●定量調査と定性調査
まずもって知って欲しい重要なことは、組合員の生活や意識がどの程度変化したかを明ら
かにするためには、定量調査と定性調査の両方が必要だということです。
たとえば調査票配布による定量調査だけでは事実を明らかにできないということです。
<定量調査>
定量調査とは、例えば、残業時間の推移、給与の推移、集会への参加率、満足と答えた人数
など、実態調査や意識などのアンケート用紙を配布して回答収集したり、数をカウントしたり
という手法を用いるもので、対象の量的な側面に注目し、数値を用いた記述、分析を伴う調査
方法です。
定量調査は、資源の適性配分、資源の集中のさせ方、活動の進捗状況の把握と数量的な効果
を調べる場合には不可欠です。
ただし、定量調査では、なぜそうなのか、どうしたらそうなるのかなど、より具体的で緻密な
事柄について明らかにすることが難しいのです。
(よくアンケートをやってもムダだと、思っている方は、この定量調査の欠点を指摘している
ものと思われます。
肝心要の部分は定量調査だけでは明らかにされません、従って、補足するように定性調査を
実施しなければならないのです。)
<定性調査>
定性調査とは、例えば、インタビューや実験や観察、文章記録や対象を映像録画した内容
分析、行動を共にしての参与観察、各種フィールドワークなど、多彩な手法を用いて質的な
データ(定性的データ)から調べる方法です。
ドラッカーは、例えば1年ごとに結果を振り返って、「われわれは何を達成できたか?
成果を得るために、われわれは何に焦点をあてるべきか?」と問いかけることで、成果を
明らかにすることがあると指摘しています。
しかし、定性データは、直感や個人的印象によることが多く、信頼性や客観性に乏しいと
の問題点があります。(そのため、定量調査を併用する必要があるのです。)
<調査の必要性>
組合員の声に注意深く耳を傾け、彼らが何を価値あるものと思っているのかについて定量
的および定性的について、知恵を使って考えるのです。
そうすることによって、組織のどの部分を評価し、判断すべきかがわかってくるし、組織に
とっての価値(効果効用は何か)成果とは何か? 上手くいっていること、そうでないもの
は何であるかが、明らかになるのです。
次回に続く・・・。
以上、何かのネタになれば幸いです。