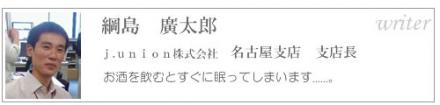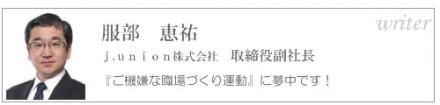先日、義祖父が90歳の誕生日を迎えました。家族で旅館に泊まり、卒寿祝いを行いました。お祝いの席では、曾孫にあたる我が家の子どもたちはそろばんやバレエを披露。私も恥ずかしながらモノマネをやらされました。90年を生き抜いて、家族から愛されている義祖父はきっと幸せな人生を実感していることと思います。
さて、日本国憲法の第13条にはこう記されています。「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」幸福追求権と呼ばれる国民の権利です。
労働組合は組合員の幸せを実現する組織です。なかには、苦労や困難で必ずしも幸せな日々を過ごしていない組合員もいると思います。けれど忘れないでいましょう。私たちは誰でも幸せになる権利を持って生まれてきたということを。幸せだったと言える人生を送れるように、支援するのが私たちの役割なのだと。モノマネを強制的にやらされる私にも、きっと幸せになる権利があると信じています。
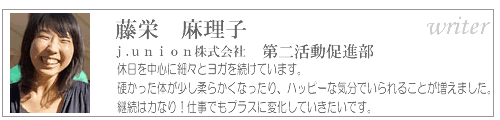
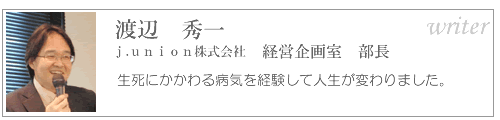
この夏、ポケモンのキャラクターを用いた位置情報連動型ゲームであるポケモンGOが大流行しました。私が勤務する名古屋市では、市内で桜の名所として有名な鶴舞公園がこのゲームの「聖地」とされ、連日多くの人々であふれかえっています。ゲームの公開とともに急遽大量の人々がスマートフォンを片手に訪れるようになったため、その模様はニュース番組でも報道されることになりました。こうしたポケモンGOの流行現象について肯定的な意見も批判的な意見も様々にありますが、ここでは私たちが行う空間に対する意味づけに注目してみたいと思います。
ポケモンGOをプレイしていると、それまで全く気にも留めていなかった場所に意味が生まれます。例えば、それまでは誰もがただ通り過ぎていただけの道角が、ゲームに必要なアイテムが手に入るポケストップになっていることがあります。その結果、私たちはその空間に「駅に向かう途中でポケストップが手に入る便利な道角」という新しい意味を与えることになります。
しかし、こうした現象は何もポケモンGOのような位置情報連動型ゲームに限ったことではありません。むしろ、もっと日常的な現象だと言えるでしょう。待ち合わせに便利な場所、パワースポットやデートスポット、高校野球の聖地としての甲子園など、私たちは様々なかたちで空間に意味を与えることで社会生活を営んでいます。そして、その意味は一定で不変というわけでもありません。古地図を手にして町歩きを楽しむ人々がいるように、私たちは空間が時間とともにその風景や意味を変化させていくことを知っています。
ポケモンGOがその流行とともに社会問題化した背景には、このゲームが同時多発的に日本中のあらゆる場所で新しい空間の意味を生み出すことで、もともとあったそれぞれの空間の意味の秩序と競合し、人々が予測していなかった変化を引き起こしているからだと考えることができるのではないでしょうか。
労働組合の活動にとってはやはり職場こそが最も重要な空間だと言えるでしょう。職場もまた空間である以上は、その意味を変化させているのかもしれません。例えば、かつては「職場集会が定期的に開かれる場所」だった職場がその意味を失いつつあるという悩みを組合役員の方々から聴くことがあります。職場が職場である以上、そこが働く場所であることは変わらないかもしれません。しかし、労働組合にとっての職場とは、単に組合員が働く場所であるだけでなく、職場役員が組合員の意見に耳を傾ける場所、執行部の方針を職場役員が伝える場所、課題解決が行わる場所、組合員が働きがいを実感できる場所だったりします。そうした職場という空間の意味は、常に人々の振る舞いによって新しく生まれたり、その内実を変化させていきます。「あの人に相談すれば、職場の課題が解決できる」、そんなポケストップのような職場のリーダーが、組合員にとって真に働きがいのある職場を作っていくのかもしれません。
夏から秋にかけて日本中の労働組合で新しい活動の期がスタートします。私にとっては新任役員研修で多くの職場役員と出会う季節でもあります。全国でポケストップのような職場のリーダーが新しい一歩を踏み出せるように努力を重ねたいと思います。