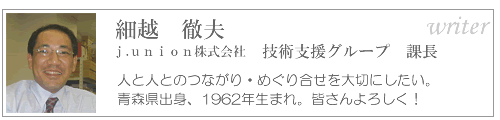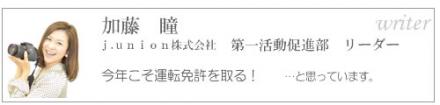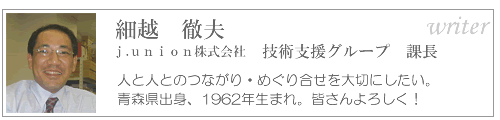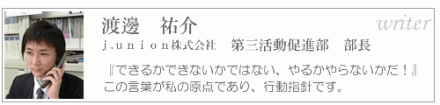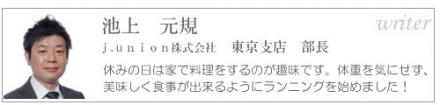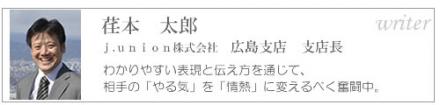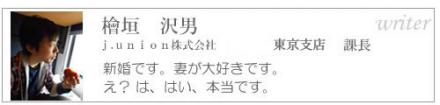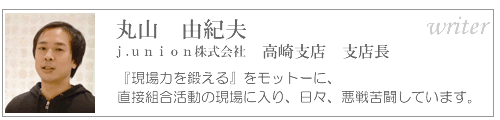みなさん、最近ワクワク、ドキドキそんな体験をしてるだろうか。
私が関わっている職場づくり運動では、集団としての感情を改善するアプロー
チを活動で実践してるが、このワクワク、ドキドキという感情をとても大切に
している。
感情の種類としては、このような感情を高揚感と言っている。
高揚感は、安心感をベースとして成り立つ感情だが、前向きにそして自分から
興味をもって取り組むための大切な原動力になる。近頃この高揚感がなくなり
かけている自分を感じ、「こりゃまずい」と思っていたところ、最近それが見
つかった。それをご紹介したい。
アーサーCクラークの小説「2001年宇宙の旅」(1968年)をご存じだろうか。
すでに小説が発表されてから50年近くが経過している不朽の名作だ。
実際には、小説よりもスタンリー・キューブリック監督の「2001年宇宙の旅」
の映画を見て知っているという方も多いと思う。実は私もその口である。
映画はその後、何度も放映されイントロで流れるテーマ曲とともにとても印象
深く私も大好きな映画の一つである。
確か小学生の4・5年生のころ、両親と一緒に市街の映画館の前を通ったとき、
大きなドーナツ状の宇宙ステーションがオブジェとして飾られていたのが、
あまりにも印象深く、いまだにその時の情景とともに記憶に残っている。
この映画、SFではあるものの、一方で人間という種の進化を踏まえつつ、未来
の人間像や人とは?などという哲学的なところがある。種の進化に影響を与え
るモノリスが出てくるかと思えば、人工知能を搭載したコンピュータHAL9000
が登場する。
初めてこの映画を見たとき、冒頭の単調な原始時代の風景シーンに違和感を感
じた。PRポスターに印刷されていた宇宙ステーションのイメージからは、ス
ターウォーズやスタートレックのようなアクションもののSFを想像していた
が、なぜか猿(類人猿)が群れて生活している単調なシーンから始まり、この
シーンが長く期待外れの映画なのかと思ってしまった。しばらくすると、突然、
猿の群れの中にモノリス(石の板)が現れ、猿たちが騒ぎだすシーンになる。
そしてシーンは、一匹の猿が動物の骨塚に迷い込んで、骨で遊んでいるシーン
を映し出す。猿はたまたま骨で頭蓋骨をたたく。すると頭蓋骨が割れる。猿は
何度も何度もそれを繰り返す。そして次の瞬間、道具を使うことで自分よりも
強いものに対抗することができることを会得したような瞬間の描写が流れる。
猿から人間に進化した瞬間を象徴的に描いている。このシーンを見るたびに、
決定的な進化が起こるのは徐々にではなく、劇的に、そして瞬間的なことなの
かもしれないと思ってしまう。その後、場面は一気に未来へ切り替わり、宇宙
ステーションの映像になる。そして、宇宙ステーションから飛び立った飛行船
に乗って航行するなかで、人工知能を搭載したHAL9000が登場する。
ここ最近、コンピュータ科学や脳神経科学の世界では、にわかに2つのキー
ワードに関心が集まっている。「人工知能」(AI)と「シンギュラリティ」
(技術的特異点)に関する事である。「シンギュラリティ」は、2045年問題と
も言われる議論のキーワードだが、人工知能が人間の能力を超える転換点のこ
とを指す。人工知能が人間の能力を超えると、つまりコンピュータが「独自に
思考し、判断し、直感を働かせること」ができるようになれば、その時点から
ものすごい速さで社会全体が進化を遂げるだろうと考えられている。したがっ
て、シンギュラリティが起こった前後では、劇的に既存の概念がひっくり返り、
爆発的な速さで世の中が変わってしまう。まさにSFとしか思えないような状況
が起こるかもしれない。「かもしれない」なのだが、それが、まんざら夢物語
でもなさそうなのである。
5/15に放送されたNHKスペシャル「天使か悪魔か 羽生善治 人工知能を探る」
の特集は、まさに夢物語から現実味のある話題として驚きだった。「そう遠く
ない未来に人工知能ができるのかもしれない」といった驚きと期待、そして人
工知能がもたらすインパクトの深さが収録されていた。
番組では、プロ棋士の羽生善治が人工知能の研究開発をしている最前線の現場
を訪問し、現地インタビューを交えながら「人間にしかできないことって、い
ったい何なんだろう」という知性への探求をするというドキュメンタリーにな
っている。
番組は、韓国のリ・セドル九段が、ディープマインド社の開発した人工知能「
ディープラーニング」を使って造られた「アルファ碁」に通算成績1勝4敗で大
敗した試合の模様から始まる。
その後、グーグル社傘下のディープマインド社の本社があるイギリス、シンガ
ポール、中国と各国の人工知能研究の最前線をめぐる。そして、日本の人工知
能研究の最前線も取り上げられていた。各企業では独自の人工知能開発の競争
が繰り広げられているが、
まだ、科学者が最終目標とする人工知能は完成していないし、いつ完成するか
も予想は難しい。最大の課題は、人間にしかないと言われている「創造性や直
感」といった「理屈抜き」で結論を導く「感情」の仕組みの解明である。
ところで、人工知能の身近な活用現状に目を向けると、ネットショッピングを
はじめとするネットワークサービスへの活用例がある。例えばアマゾンで書籍
などを購入される方も多いと思うが、最近では書籍だけでなくありとあらゆる
商品の購入が可能である。購入経験のある人が、アマゾンにログインすると、
過去に購入したり検索したりしたその人の関心ごとに関連した商品がバナー広
告などで表示される。購入回数や購入する商品の分野が広ければ広いほど、そ
の人の興味をそそる商品広告が表示される。これこそ、進化中の人工知能の活
用例である。アマゾンのサイトの中で、自分の興味や関心に基づいて利用すれ
ばするほど、その人の指向する情報が掲載される。アマゾンのサイトを構成す
るプログラムに組込まれた人工知能が学習しているわけだ。
また、独立したロボット型の人工知能というものもある。スターウォーズに登
場するC-3POのような人間型ロボットがその代表格だが、アシモフやペッパー
といった独立系ロボットも実際に販売されている。我が家にも、ちょっとした
人工知能搭載のロボットがいる。S社から発売されている「ココ○ボ」くんと
いうロボット掃除機である。部屋の間取りや障害物などを記憶し、使うほどに
掃除がうまくなっていく。また本来の掃除機能だけでなく、人間とのコミュニ
ケーションを図る「おしゃべり機能」も搭載している。とうてい本来の人工知
能とまではいかないが、音声認識エンジンを搭載し、「おはよう!」といえば
「おはよう!」と返してくれる。「きれいにして」といえば、「了解!」と応
え掃除を始める。掃除中も、「あー忙しい、忙しい」としゃべったり、突然話
し始めたりもする。そんなココ○ボを面白がって家内は、楽しそうに利用して
いる。
人工知能をSFの世界、最先端の現場、日常生活とでそれぞれ人工知能について
取り上げてみた。先の番組中でも、医療現場での診断や自動車の自動運転、S
NSでのサービスなどで、人工知能を採り入れる可能性は極めて高い。そして
一般的な日常生活の中でロボットが活躍する日もそう遠くはないだろう。もし、
人工知能が完成し、その後シンギュラリティが起ったとして、危惧されている
問題は本当に起こるのだろうか。
願わくば、人工知能の完成形が、人の心を察して、気遣い、ねぎらう、そんな
人間のよい感情を基軸にしたものになればと願うばかりである。
さて、この社会には数限りなく正解のない、解明できていない「なぜ」がある。
「なぜ、人間は生まれて死ぬのか」「なぜ、負けるとわかっていても戦うのか
」
「なぜ、男・女が存在するのか」「なぜ、発展し続けるのか」
「生命の根源はどこにあるのか」
いずれも正解がない問題ばかりである。また、それほどまでに究極の問題では
ないけれど正解のない問題というのは、社会の中で常に付きまとう。
また、組織や人と人の関係にもこうしたら正解といった問題ばかりではない。
もし人工知能が完成したなら、その人工知能に質問してみたい「なぜ?」を。
どんな答えを返してくれるのだろうか。
到底、私の生きている間には無理だろうと思っていた遠い遠い未来の話が、も
しかすると自分が生きている間に体験できるのかもしれない。
そんな人工知能が実現した社会を怖い・恐ろしいという思いもあるが、そんな
社会を体験してみたいという気持ちが勝ってきている。
まさにワクワク、ドキドキそんな気持ちが、自分の中で大きな活力を生み出し
始めている。