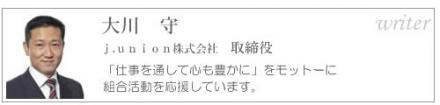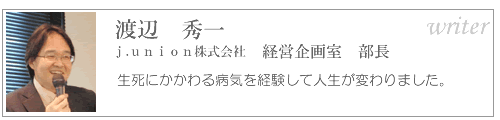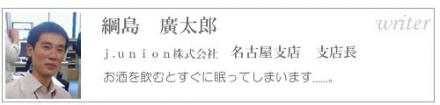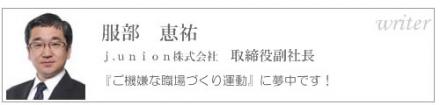19世紀のフランスの心理学者・ピエール・ジャネという人が、主観的に記憶される年月の長さは年少者にはより長く、年長者にはより短く評価されるという現象を著書に書いています。これは「ジュネ―の法則」と呼ばれるもので、50歳の人にとっては、1年は50分の1になるけれど、10歳なら1年は10分の1の感覚になるので、年齢が若いほど1年間が長く感じるそうです。日常でも、往路は長く感じるけれど、復路は短く感じるものです。
同じ時間を過ごしても新たな刺激が少なければ、どうしてもマンネリになります。仕事でも新しい業務に取り組まなければ、振返った時に「今年は何をした1年だっただろう?」と印象に残らない年になることでしょう。
「今年はこれをやった」「あの年はあれにチャレンジした」、2016年を5年後・10年後に思い出せる1年にしたいものです。年度が変わって、環境を変えて新しい事にチャレンジする人も多いと思いますが、何かひとつやったことがないことに取り組んでみてはいかがでしょう(私は今年、大嫌いなジェットコースターにチャレンジしました)。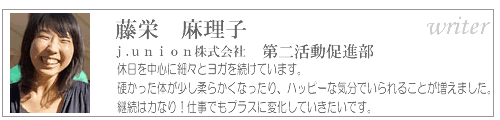
デフレマインドで世の中が萎縮している
バブル崩壊後の長引くデフレ、中国経済の成長鈍化、欧州諸国の財政悪化など、日本でも世界規模でも経済的な将来の展望が見えにくくなっている。一方で国内大手企業の業績予想では、過去最高益が確実視される企業群が多いかと思えば構造不況から脱しきれない企業も多く、業績回復に著しい格差が生まれてきている。
アベノミクスで大胆な金融緩和・マイナス金利政策をしようとも多くの企業は設備投資に資金を充当せず、正社員採用を増やさず、従業員の賃金を大幅に増やすこともなく、内部留保を増やし溜め込んでいる。
先行きの不安から現状維持型や縮小均衡型になり、成長軌道を描かない企業の姿は慎重さを超え、経営が萎縮しているように見える。まさに経営者の胆力が問われるところではないだろうか。
お金は足りている。回していないことが問題だ
「堅実な経営」と呼べば聞こえは良いが、下請け業者への発注価格を極限まで押さえ込み、本人が望まずして非正規社員のままでいる「不本意非正規社員」の比率を高めているようなことはないだろうか。さらに正社員には過重労働を課して賃金を抑制するというのであれば、単なる“ドケチ経営”でしかない。
短期的に経営指標の改善は進むかもしれないが、長い目で見れば競争力が高く尊敬される企業になり得るはずがないのは明らかだ。
また、そのような“ドケチ経営”が増えてくると世の中にお金が回らなくなり、経済自体がしぼんでしまう。今の日本がまさにそうであり、「決算良し、景気悪し」という合成の誤謬に陥ってしまっている。外貨を獲得してGDPを600兆円にするよりも、今あるお金を循環させることのほうが景気は良くなるのだ。
生み出す付加価値を適正価格に転嫁せよ
“ドケチ経営”をしている多くの経営者も、当然ながら人間性に問題があるのではなく、経営努力が会社の収益に反映されにくい難しい時代だからこそ経営の舵取りに悩んでいるのであろう。わが国の企業は誠実な従業員の献身的な努力で付加価値の高いモノづくりやサービスを実現している。それにもかかわらず、生み出す付加価値に見合う価格で取引できていない「商売ベタ」になり採算性が低いのが悩みの原因だ。
B to C のビジネスでは、モノやサービスの販売時の過当競争で値崩れが起きる。B to B ではアッセンブリーメーカーなど発注者側からの厳しい値引き要請に応えざるを得ない厳しい企業間の過当競争が存在し、サプライヤーは十分な利潤が得られない状況も続いている。
自社の利益だけに固執しない、社会の公器としての企業のあり方
故・松下幸之助氏は「企業は社会の公器なり」という金言を残されたが、このような時代だからこそ強く共感できる考え方だ。資本主義・民主主義国家としての社会システムの中での企業という視点で考えたい。企業は本業として生み出すモノやサービスだけで社会に貢献するのではない。企業活動の中で多くの雇用を生み出し、雇用労働者の消費拡大によって景気は浮揚する。法人税による貢献もあれば、労働者による納税や地域貢献もある。さらに自社だけではなく数多くの取引先との公正な価値交換活動によって取引先の企業にも雇用や消費拡大の芽が生まれる。
労使の協力で多くの付加価値を生み出し、適正利益を上げるとともに取引先の存続発展にも寄与する共存共栄型の公器であってほしいと願いたい。
私は労働組合役員にも、経営側とこのような価値観の共有を図ってほしいと考えます。