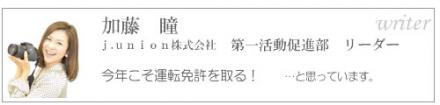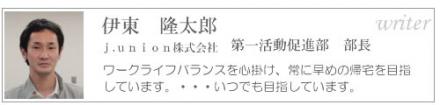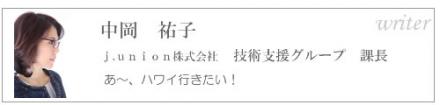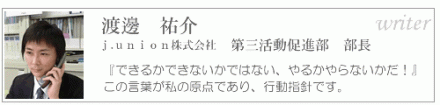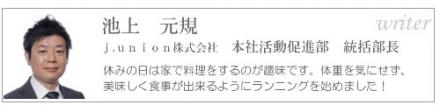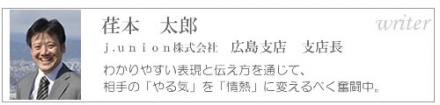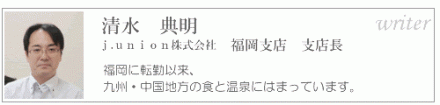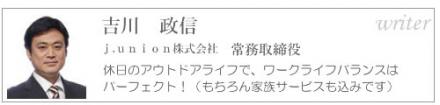先 週、関東地方では春一番が吹いたために風が強く、さらには雨まで降っていたのでまるで台風が来ていたかのような週末でしたね。春一番とともに花粉が飛散し 始めたとのことで、「花粉情報」がニュースで流れてからなんだか鼻がムズムズするような、目がかゆいような、そんな気がしています。
5年ほど前から花粉症に近い症状が出てはいるものの軽く、鼻がムズムズしても薬を飲まずになんとか日常生活を送ることができています。なので「私は花粉症ではない!」と思い込んでいます。
そう、実は病院で検査をしていないのです。
病院で「花粉症」と診断結果が出たとたん、いっきに悪化してしまうのではないかと思い、怖くて行っていません。
それは、そんなに具合が悪いわけではないけれど風邪ぎみかもしれない…と思ったときにふと体温を計り「37.5℃」と表示されたとたん、「熱が上がってくる」「ぜったい風邪だ」と思い、さっきま での「そんなに具合が悪いわけではないけど…」という自覚がどこかに消え去り、だんだん具合が悪くなってくるのと一緒で、特に花粉症に関しては「病は気か ら」だと思っているところがあるからです。
その本の中でマクゴニガル氏は「ストレスは健康に悪い」と思うと死亡リスクが高まる、と言っているのです。それは1998年にアメリカで成人3万人を対象に行われた調査と8年後の追跡調査からわかったというのです。
強度のストレスがある場合に死亡リスクが43%高まるのですが、 そのリスクが高まったのは強度のストレスを受けていた人のなかでも「ストレスは健康に悪い」と考えていた人たちだけでした。さらに、強度のストレスを受け ていた人の中で「ストレスは健康に悪い」と思っていなかった人たちの死亡リスクは対象者のなかで最も低く、なんとストレスがほとんどない人たちよりも低 かったというのです。
またマクゴニガル氏は「ストレスは役に立つ」と思うと現実もそうなると言っています。「ストレスには良い効果がある」というビ デオを見た人たちは、「ストレスは心身を消耗させる」というビデオを見た人たちに比べ、ストレス反応の「成長指数」(※)が高く、ストレスに負けずがんば ることができ、また集中力が高く、問題解決力に優れ、心的外傷ストレスの症状が表れにくい傾向も見られたというものでした。
(※コルチゾールに対するDHEAの割合。割合が高いと不安症、うつ病、心臓病、などのストレスに関する様々な病気のリスクが低下する傾向が見られる。)
このような思い込みの効果はプラセボ(偽薬)効果よりも強力で「マインドセット効果」と呼んでいます。またプラセボ効果は短期 的にある特定の効果のみをもたらすのに対し、マインドセット効果の及ぶ範囲は雪だるま式に増大し、ますます威力を増しながら長期的な影響をもたらすとまで 書かれています。
今までストレスは体に悪いもので、できるだけ減らすことが良いことだと思っていましたが、実はそうではなくストレスを受け入れ て上手に付き合っていくことで、健康や幸福、寿命といった長期的な結果に影響してくるというのです。ただ、ストレスの良い面をみつめるために「ストレスは 場合によっては害になる」という認識は捨てる必要がないとマクゴニガル氏は言っています。重要なのはストレスについてバランスの取れた考え方ができるよう になることで、ストレスに対する恐怖が減り、対処できる自信がわき、ストレスをうまく利用して人生としっかり向き合っていけるようになるというのです。
組合としてもメンタルヘルス対策を行っているところは多いと思います。
この書籍を読み、メンタルヘルス対策、特にセルフケアとして「ストレスとの上手な付き合い方」を組合員が正しく学ぶことの大切さを強く感じました。また、「ストレスマネジメント」の研修を行っている者としての役割の重要性も改めて痛感いたしました。
そして、「病は気から」のことわざを信じ5年間うまく付き合ってきた花粉症とは今年もうまく付き合っていけそうな気がしています。