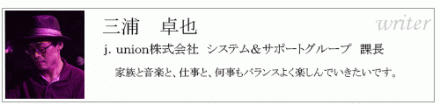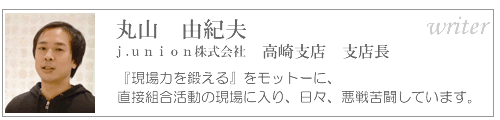| 全国3700ほどの労働組合とのお付き合いの中で、記憶に残るエピソードや、これは使えるといったネタをご紹介していくコーナーです。 |
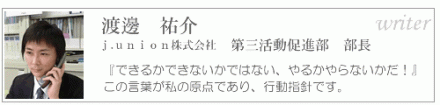
今年の11月に実家に戻り父親の三回忌を終えた。
母は72歳。愛知の実家で一人暮らしをしている。
私も普段からできるだけ電話し、出張時には意識的に実家に立ち寄るようにしている。
今回の三回忌の帰省時にゆっくりと時間が取れたので、最近は何をしているかと母に尋ねた。
母は市が主催するカルチャースクールの太極拳、PC基礎、囲碁・将棋などに通い体や頭を使っているようだ。
また、今でも自宅でできる仕事もしているようで、
心も体も元気なことはとてもありがたい。意外と充実した時間を自分で作っていいて少し安心した。
2017年1月から育児介護休業法が改正されることも重なり、
育児・介護は労使で最もホットなテーマになっているようだ。
特に介護についてはこれから課題が顕在化されてくる。
厚生労働省の「介護保険事業状況報告(年報)」(平成24年度)の算出によると、
要介護認定されている人を年齢で見ると65歳~74歳は3%(47万3千人)、
75歳以上は23%(348万9千人)となっている。75歳を超えると数字が上がり、
差は7倍になる。
今後の高齢化社会を考えると5年後、10年後、多くの組合員が介護の問題に直面することになるであろう。
今から介護離職の時代に備えて“介護離職ゼロ”と掲げ、「働き方改革」に取り組んでいる労組も増えてきている。
「働き方改革」は長時間労働問題や生産性の向上を主要課題として労使で取り組みをしているが、
介護に備えて取り組む意味合いも大きい。
私の母親も今は元気でいても、先を考えると備えや準備は必要になってくる。
そこで、厚生労働省ホームページより「親が元気なうちから把握しておくべきこと」(一部抜粋)を紹介したい。
◆質問:自分のご両親や介護にかかわることをどこまで知っていますか? 共有していますか?
□介護が必要になった場合、誰とどのように暮らしたいか
□子どもに介護してもらうことへの抵抗感の有無
□在宅介護サービスを利用するか
□介護施設に入居するか
□最期はどこで暮らしたいと思っているか
□延命治療を希望しているか
□親の1日、1週間の生活パターン
□高齢になって、生活上困っていることや不便に感じている場所
□親の経済状況(どれくらいの生活費で生活しているか、生活費を何でまかなっているかなど)
□食事のとり方
□耳の聞こえ方
□トイレ・排泄
□動く様子(歩き方、歩く速さ、つまずく、転ぶなど)
□物忘れの傾向(同じものを買い込んでいないかなど)・頻度
□親の既往歴や血圧など
□親の服用している薬(市販薬を含む)やサプリメント
□親のかかりつけ医
□親の不安・悩み
□兄弟姉妹・配偶者の介護に対する考え方
□兄弟姉妹・配偶者の親との関係性
□兄弟姉妹・配偶者の健康状態
□兄弟姉妹・配偶者のそれぞれの家庭の状況(子育ての状況、他の要介護者の有無など)
□兄弟姉妹・配偶者の仕事の状況(勤務形態、転勤の有無、残業の有無、出張の頻度、勤務先の仕事と介護の両立支援制度など)
私もこの厚生労働省のホームページの質問項目を見てまだまだ全然、
把握・共有が足りず、準備やイメージが出来ていないことを再認識した。
介護は他人ごとではなく、これから自分の生活、仕事そして経済的な部分にも大きく影響を及ぼす可能性がある。
いまから家族と十分に話し合っておくことが今できることだ。
今年の年末には母親や姉夫婦と過ごす時間があるので、
元気なうちに明るく前向きに介護の話もしておきたい。
安全啓発活動のお手伝いをしている製造業労組の役員よりうかがったお話。
「安全な状態を当たり前とするために、会社は少なくないコストをかけている。
しかし、安全設備が技術的に進化し、リスクアセスメントの精度を高めると同時に、
それらに依存し過ぎてしまう現場作業者も出てくる」
通常業務中はほぼ完ぺきな安全状態でも、それに慣れた意識のままイレギュラーな状況になったとき、
事故が起きるリスクが急激に高まるそう。
皮肉にも、稀に発生する事故やヒヤリハットが最大の安全啓発となり、
「安全意識のネジを巻き直す」きっかけとなることも。
電子制御や機械による生産性・効率性に優れた安全対策だけではなく、
それらをオペレーションする現場作業者一人ひとりにきちんと目を向ける必要があるそうです。
良い製品・商品を作り続けるには、安全は「あって当たり前のもの」でなくてはなりません。
必要なのは、設備(ツール)・手法、企業文化・行動習慣・共通の価値観(企業理念)の確立と、
一時的でない持続的実践を生む"現場力"です。
現場力とは、こと安全の領域においては
「安全をすべての業務に優先させるべく、現場にいる皆が『今、自分ができること』をできる力」
と言いかえられないでしょうか。
人命に直に関わる安全への取り組みは、労使間、部門間、役職間などの隔たりは取っ払い、
「働く人にとっての掟」として全従業員が関わっていくべきだと考えます。
「すべての結果は行動の蓄積である」
「人生を変える行動科学セルフマネジメント」の著者 石田 淳 氏によると、
良い結果が出たのは良い行動の繰り返しである。強い意志があっても行動なきところに結果は生まれないと述べている。
では人は、なぜ人は行動に移すことができないのでしょうか?
著書の中で石田氏は、悪い結果はすぐに出ない。しかも必ず出るとは限らないからであると述べている。例えば、
ダイエットしたいと思っても、食べてもすぐ太らないので、今すぐ得られる美味しい結果に流される。
喫煙においても同様で、吸い続けてもすぐ健康を害さないので、今すぐの安堵感に流される。つまり、
人は意志の通りに行動できないので、意志で行動を変えようとしても無理があるのです。
だから、思い通りに変えるためには、まずは小さな具体的な行動の蓄積をして結果を変える必要があると述べています。
では、そのために何をすれば良いのでしょうか?
①具体的にどうなりたいか明確なビジョンを持つ
どうなりたいのかが具体的でないと心が充たされることもなく、何をすれば良いのかわかりません。
いつまでにどれぐらいどうなりたいのか明確にしておく必要がある。
②そのための小さな行動を設定する
達成のハードルを低くし、すぐに結果がだせるようにスタートし、ゴールの蓄積ができるようにする。
それによって達成感を感じれるようにする。
継続できないのは、達成のハードルが高く、いい結果がなかなか得られないために、自信喪失になるからです。
だから、毎日、無理なく、数値化できる行動を習慣化し、できそうだという思い(「自己効力感」)を持たせることが大事です。
小さなステップでも確実な成功体験を積むことにより、「できた」と感じる回数が多くなることで自己効力感は増大します。
組合活動においても、現場の役員がやる気がない、動いてくれないという言葉をよく耳にしますが、自己効力感を高め、
達成感を感じるようにするためにも個々の具体的なビジョンを描かせ、それに向かって行動を起こせるように
スモールゴールを設定していくことが必要ではないでしょうか。
今後の組合活動の参考になれば幸いです。